 |
 |
 |
 |
| 由比宿東木戸跡 | 紀州藩七里飛脚役所跡 | 七里役所跡の説明板 | 飯田八幡宮参道 |
東海道(由比宿~興津宿)
| 日時・行程 |
| 2011年6月4日 |
| 由比宿東木戸跡 ~ 由比本陣 ~ 加宿問屋場跡 ~ 延命寺 ~ |
| 由比宿西木戸跡 ~ 由比川橋 ~ JR由比駅前(今宿) ~ 寺尾 ~ |
| 東倉沢 ~ 小池邸 ~ 西倉沢 ~ 柏屋 ~ 望嶽亭 ~ 西倉沢一里塚跡 ~ |
| 薩埵峠 ~ 山之神遺跡 ~ 中道 ~ 休憩所 ~ 白髭神社 ~ |
| おきつ川通り ~ 興津東町 ~川越遺跡 ~ 興津中町 ~ 宗像神社 ~ |
| 興津一里塚跡 |
| 地図 |
| 国土地理院地形図(蒲原 興津) 現地住宅地図(ゼンリン) |
 |
 |
 |
 |
| 由比宿東木戸跡 | 紀州藩七里飛脚役所跡 | 七里役所跡の説明板 | 飯田八幡宮参道 |
| 由比宿のある東海道へは車で行って由比川の右岸河原に大きな無料駐車場がある。街道を蒲原方面 |
| に少し戻り、東木戸跡の桝形を出発点とする。西に向かってすぐ右手に民家の白い塀に埋め込まれた |
| プレートを見る。ここは紀州藩が独自の連絡機関として江戸から紀州まで7里ごとに飛脚小屋を置いた |
| 跡である。役所跡の先右手には飯田八幡宮の参道がある。 |
 |
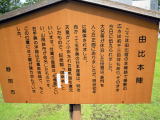 |
 |
 |
| 由比本陣 | 由比本陣の説明板 | 本陣井戸 | 本陣井戸の説明板 |
| 由比宿中心部に入ってくる。街道右側立派な門構えと板塀に囲まれた由比本陣跡は公園と広重美術館 |
| となって由比観光の中心をなしている。敷地内には当時使っていた井戸も残っていた。 |
 |
 |
 |
 |
| 本陣公園 | 本陣前の街道 | 推定 問屋場跡 | 本陣前の常夜燈 |
| 本陣の敷地は1300坪あったようで明治元年に母屋は取り壊され跡地が芝生公園になっている。 |
| 庭内に残っているものは左側奥に離れの日本家屋と物見塔ぐらいである。本陣の表門脇には秋葉山 |
| 常夜燈が建っている。これは寛政11年と刻字があった。また本陣向い側やや東に鍵屋問屋場があった |
| ようだが今では全くその跡形もなく推定するにすぎない。 |
 |
 |
 |
 |
| 大法寺参道 | 大法寺 | 本陣前馬の水呑場 | 馬の水呑場の説明板 |
| 本陣公園の東側に新しく建てられた由比宿交流館の東隣に大法寺の参道が北に入っている。本陣の |
| 東北に隣接する大法寺は本陣に宿泊した貴賓の避難所にもなっていたという。また表門の脇に伸びる |
| 石垣と板塀の前には今ではきれいに整備されている馬の水呑場という遺構が残されている。当時は |
| 幅1m長さ20m深さ60cmもあって大名行列の馬に水を飲ませたり洗ったりした所らしい。 |
 |
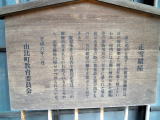 |
 |
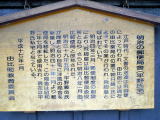 |
| 正雪紺屋(由井正雪生家) | 正雪紺屋の説明板 | 明治の郵便局舎 | 明治の郵便局舎の説明板 |
| 本陣の正面西寄りに正雪紺屋と明治の郵便局舎が並んでいた。江戸時代初期の頃から紺屋(染物屋) |
| として続いている建物は当時の風情たっぷりであり、また慶安事件で有名な由井正雪の生家としても |
| 名を馳せている。その西2軒隣は平野氏宅の明治39年に建てられた郵便局舎である。 |
 |
 |
 |
 |
| 饂飩屋脇本陣 | 饂飩屋脇本陣の説明板 | 加宿問屋場跡の松風堂 | 加宿問屋場跡の説明板 |
| 由比宿に3軒あったとされる脇本陣の内、江戸末期最後まで勤めていたとされる饂飩屋脇本陣は本陣 |
| 向いの正雪紺屋と郵便局舎の間で黒板塀があり3軒の内で一番旧態をとどめている。本陣の西側には |
| 正法寺の参道があって、入口西側の現在菓子店を営んでいる松風堂が加宿問屋場の跡である。由比 |
| 宿の加宿に指定された北田・町屋原・今宿など11ヶ村が共同で問屋場を設営した所であった。 |
 |
 |
 |
 |
| 正法寺参道 | 羽根屋脇本陣 | 羽根屋脇本陣の説明板 | 延命寺 |
| 正法寺参道から加宿問屋場を過ぎて西側のならびに羽根屋脇本陣があった。羽根屋は徳田屋が寛政 |
| 年間に衰微したので替わってつとめた脇本陣であった。ここは隣宿江尻の羽根本陣の分家であったと |
| いう。徳田屋脇本陣跡の西側を入ると延命寺があって本堂向拝の蟇股に彫られた2匹の龍が目を |
| 引く。 |
 |
 |
 |
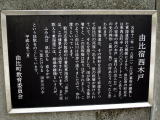 |
| 徳田屋脇本陣 | 徳田屋脇本陣の説明板 | 由比宿西木戸跡 | 西木戸の説明板 |
| 延命寺入口に脇本陣の徳田屋はあった。江戸の後期には衰微したため、その後には羽根屋が代って |
| 脇本陣をつとめたようである。現在でも徳田屋の屋号を使って文具店が営まれていた。もうこの先は |
| 由比宿の西のはずれになってくる。今の道はまっすぐ由比川に架かる由比川橋に向かっているが、 |
| 当時は左に分かれた道を行って桝形になった西木戸を左折して河原に降りて仮の板橋を渡ったという。 |
 |
 |
 |
 |
| 入上地蔵堂 | 入上地蔵 | 西木戸桝形と入上地蔵説明板 | 西木戸桝形から河原へ |
| 西木戸の所に小さな祠が建っている。中には何体かの地蔵が祀られていて説明板によると、由比川 |
| は一度大雨があると急な増水があり水難者が多く出たそうだ。そこでこの地に地蔵を祀って供養して |
| いるとのことである。桝形から河原と対岸をみると現在はそんなに水量が多くはないようで、対岸に |
| 旧道らしき細い道が伸びていた。 |
 |
 |
 |
 |
| 由比川橋 | 常夜燈 | 由比川橋を渡る | 妙栄寺参道 |
| 桝形から元の街道(県道370号)に戻り由比川橋を渡る。橋を渡る手前に1基の常夜燈が建っていた。 |
| 刻字を見ると文化丙寅12月となっているから文化3年(1806)のものであり火袋から上の部分が |
| 入母屋屋根が乗り珍しい形をしていた。由比川橋の上から南を見るとすぐそばにJR東海道線、国道 |
| 1号、東名高速と3本並行して走っている。橋を渡ると右手は妙栄寺参道。 |
 |
 |
 |
 |
| せがい造と下り懸魚の家 | せがい造と下り懸魚の説明板 | 地持院と豊積神社の参道 | 由比港入口 |
| 街道を西進すると左手に屋根が3重になったような民家が見えてくる。大きく軒を前に出した重みを |
| 支えるため桁をさらに出した、せがい造というそうで由比に多く残っている。また桁の先には社寺建築 |
| にあるような下り懸魚の装飾を施してある。やがて右手には豊積神社と隣接する地持院への参道。 |
| その先は左に入る由比港への道。このあたりは名産のさくら海老が天日干しされている風景が目立つ。 |
 |
 |
 |
 |
| JR由比駅 | 由比駅前の今宿道標 | 由比駅前から薩埵峠方向 | 歩道橋を渡り寺尾地区へ |
| JR由比駅は由比宿中心部から西方に北田・町屋原を過ぎて今宿にある。およそ1kmくらいか。この |
| 東海道は現在県道370号になっているが、由比駅前を通り過ぎた所で県道396号に合流する。合流 |
| 地点に架かった歩道橋を渡り北側の細い道に入って行く。 |
 |
 |
 |
 |
| 寺尾地区の町並 | 寺尾地区の説明板 | 小池邸 | 小池邸の説明板 |
| 県道と離れ寺尾地区に入る。ここから東倉沢・西倉沢と薩埵峠まで旧街道の面影の残る風情ある町並 |
| が続いている。何か取り残されたような、いや大事に保存されているような風景に浸ってしまうものだ。 |
| 寺尾地区の中心地北側に江戸時代に代々名主を務めていた小池邸の大きな屋敷がある。現在の |
| 建物は明治時代のものだが国の文化財指定をうけている。 |
 |
 |
 |
 |
| あかりの博物館 | 八坂神社 | 宝積寺 | 西倉沢の町並 |
| 小池邸の筋向いにはなまこ壁の目立つあかりの博物館。以前訪問して見学したことがあるが、時代ごと |
| にそれぞれ道具類が展示されなかなか興味深い思いをした。さて東倉沢に入って右手急斜面に八坂 |
| 神社が祀られている。このあたりの地形は駿河湾の海岸線まで山が迫っておりその山裾に集落が張り |
| 付いたように長く伸びているので当然に社寺は斜面の急階段上にある。西倉沢に入って宝積寺。 |
 |
 |
 |
 |
| 間の宿柏屋脇本陣 | 柏屋の説明板 | 望嶽亭藤屋 | 望嶽亭説明板 |
| 西倉沢の町並。江戸時代の当時そのままのような家並みが続く。ここは由比・興津両宿の間の宿と |
| なっていた。街道左手南側に大きな脇本陣柏屋が目立っているが、その少し手前に本陣跡がある。 |
| 柏屋は明治時代になって天皇の御東幸の折にも休憩所となったようだ。柏屋のならびで薩埵峠の |
| 登り口の所に望嶽亭藤屋があった。ここからの富士山の眺めがよく文人墨客の好みであった。 |
 |
 |
 |
 |
| 西倉沢一里塚跡 | 一里塚の説明板 | 薩埵峠の登り口 | 登り口に建つ倉沢の標識 |
| 西倉沢望嶽亭前に一里塚跡を示す石柱があった。今では塚らしいものは全く見られず、本来の位置も |
| 不確かなようだ。江戸から40番目にあたる。ここの地名が坂口と呼ばれているように薩埵峠への登り |
| 口である。石柱の反対側に倉沢の標識が建てられていた。 |
 |
 |
 |
 |
| 急坂を登る | 坂の上から見た薩埵峠方向 | 薩埵峠の標識 | 薩埵峠地蔵道標 |
| いよいよ薩埵峠東口の急坂が始まる。距離はそれほどないが一気に登りきると南側が開け駿河湾 |
| から前方に薩埵峠方向、三保の方まで展望がきく。眼下には東名高速と国道1号が交差している。 |
| 周りの傾斜地には名産のビワと夏みかんが色づいていた。農家の収穫が忙しそうだ。やがて道は |
| 平坦になって薩埵峠の標識が見えてくる。横に延享元年6月の地蔵道標も建っている。 |
 |
 |
 |
 |
| 峠に建つ 薩埵山合戦の説明板 | 薩埵峠からの駿河湾と富士山 | 上道と中道の分岐 | 薩埵峠山之神遺跡 |
| この地薩埵峠付近は2度の戦場になったことがある。14世紀の足利尊氏・直義兄弟の争いと16世紀 |
| 甲斐の武田勢が駿河侵攻をして今川氏真と戦った時であった。東国から西に向かうのには急峻な |
| 峠道を通らねばならず戦の場になったのであろう。峠の標識から先に分岐があり上道から登ってきた |
| 道が中道と合流。広い駐車場と休憩スペースになっていた。山之神遺跡の石柱も建つ。 |
 |
 |
 |
 |
| 中道を降りる | 展望台 | 展望台から見た富士山 | 薩埵峠の歴史説明板 |
| 休憩スペースの遺跡石柱の裏側から中道は下っている。舗装はされていないが歩きやすいハイキング |
| コースになっている。2~3分も下ると展望台があり、ここからの富士山の眺めは薩埵峠というと必ず |
| ここからの富士山が出てくるという風光明媚を絵に描いたような場所。今日晴れてはいるが北の方角 |
| が霞んで残念であった。 |
 |
 |
 |
 |
| 急な階段を下りる | 下った所の墓地と休憩所 | 休憩所と駐車場 | 休憩所前の緩い坂を下る |
| 展望台からは急な階段を下る。しばらく降りていくと開けたところに墓地が見えてきた。墓地の間を |
| 通り左側に休憩所と駐車場。上道コースは峠手前の薩埵峠山之神遺跡がある休憩スペースまで |
| 車で入れるが、中道コースは墓地前の駐車場までである。休憩所前からは舗装道路を緩やかに |
| 下っていく。 |
 |
 |
 |
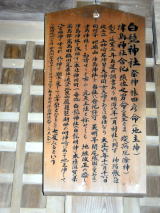 |
| 白髭神社前中道と下道の分岐 | 白髭神社 | 境内の常夜燈 | 白髭神社の由緒書 |
| 緩やかな坂を下ったところの十字路。中道は右折して興津東町内洞地区に降りていく。左折すると |
| 下道コースで白髭神社を回りこんでJR東海道線ガードをくぐって興津中町に出る近道である。地図 |
| によってはこれが中道となっているものもある。白髭神社は延宝3年というから1675年創立の祭神 |
| 猿田彦と天明年間に津島天王社を合祀した神社である。明治8年の常夜燈も建っていた。 |
 |
 |
 |
 |
| 中道の下りにある常夜燈 | 秋葉山常夜燈 | おきつ川通(正面は興津大橋) | おきつ川通(右は峠へ近道) |
| 白髭神社の十字路交差点を右折して内洞方面に中道は迂回している。当時は下道が絶壁の波打ち |
| 際を通っていたことから明暦元年(1655)に迂回路が開かれたようだ。中道下りの途中左手に秋葉山 |
| 常夜燈が建っていた。文政2年11月と刻まれている。内洞地区で山裾を回りこむ方が近かったし本来 |
| の中道であったが少し先を回っておきつ川通りに出た。直進すると興津大橋、左折して南下する。 |
 |
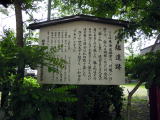 |
 |
 |
| 興津川川越し跡 | 川越遺跡の説明板 | JR東海道線のガードをくぐる | T字路に出て右折(下道と合流) |
| 興津川に沿って南下して行くと途中で山裾を回ってきた近道と合流する。やがて興津東町公会堂の前、 |
| 小公園に説明板が建っているのに気がつく。この地が興津川の川越えをするところで天和3年の川越 |
| 人足の料金が書かれていた。公園で小休止してからJR東海道線のガードをくぐり橋に上ったところの |
| T字路を右折する。ここで下道と合流。 |
 |
 |
 |
 |
| 興津川を渡る | R1と接する場所 | 興津中町交差点(右はR52) | 宗像神社参道 |
| 興津川を渡るともうJR興津駅までは1.6kmの表示がある。橋のすぐ南側が国道1号の橋、そのすぐ |
| 南側は興津川河口と駿河湾である。しばらく歩いていくと国道1号に接するがそのすぐ先の興津中町 |
| 交差点があり、国道に入るにはここからである。興津中町交差点は右折するとここは国道52号で |
| 興津川やがて富士川に沿って甲府方面に行く。交差点の向こう側に宗像神社が建っている。 |
 |
 |
 |
 |
| 身延道説明板 | 石塔寺跡の題目塔 | 七面山常夜燈 | 身延山道の道標 |
| 宗像神社の参道入口の前を通過して右手に身延道の入口があり身延山参詣の道とともに駿河・甲斐 |
| の交易の道でもあった。街道脇に題目塔と七面山常夜燈が残っているが、日蓮宗法華題目堂であった |
| 本堂は明治以降廃寺となって現存していない。なお常夜燈横の道標刻字に元禄6年10月とあった。 |
 |
 |
 |
 |
| 身延道 | 興津一里塚跡 | 一里塚跡の石柱 | 一里塚前の街道 |
| もうこのあたりから興津宿に入っているものと思われるが、東木戸跡を示すような枡形も表示もない。 |
| 街道右手北側の佐藤正明氏宅右脇に小さな石柱が建てられていて、気がつかずに素通りしてしまい |
| そうなこの地に興津一里塚があったようである。江戸からは41番目だ。興津宿については次回に |
| ゆっくり見学することにしてJR興津駅から帰宅する。 |