 |
 |
 |
 |
| 新町橋(三島宿東木戸) | 光安寺 | 守綱八幡神社 | 妙行寺 |
東海道(三島宿〜沼津宿)
| 日時・行程 |
| 2010年5月4日・5月22日 |
| 新町橋(三島宿東木戸) 〜 三嶋大社 〜 本陣跡(本町) 〜 広小路 〜 |
| 西見付(加屋町) 〜 千貫樋 〜 伏見一里塚 〜 黄瀬川橋 〜 傍示杭(石) 〜 |
| 沼津一里塚 〜 日枝神社 |
| 地図 |
| 国土地理院地形図(三島・沼津) 現地住宅地図(ゼンリン) |
 |
 |
 |
 |
| 新町橋(三島宿東木戸) | 光安寺 | 守綱八幡神社 | 妙行寺 |
| 箱根西坂を下り大場川に架かる新町橋を渡ると三島宿に入る。橋の西詰に東の見付があったが、今は |
| 全くその形跡はない。通りの右手(北側)に時宗の光安寺。地蔵菩薩は鼻取地蔵とよばれ市の文化財 |
| に指定されている。光安寺の手前街道沿いに守綱八幡神社が祀られていて、境内の常夜燈は安永 |
| 6年に奉納されたと刻まれていた。その向かい側に題目塔が建ち、参道を通って妙行寺。山門がそう |
| とう古そうだ。玉沢の妙法華寺末の日蓮宗寺院で臨時に休泊も引き受けたそうだ。 |
 |
 |
 |
 |
| 成真寺 | 日隅神社 | 本妙寺 | 旧伝馬町の標識 |
| 妙行寺のすぐ西に成真寺。浄土真宗大谷派の古寺で特に鐘楼門が堂々と建っている。ここは寺院の |
| 並ぶ地域でまた西側に本妙寺。だが、その間に日隈神社がある。三嶋大社の摂社で大国主命が |
| 祀られている。本妙寺は慶應元年に造立された題目塔から続く参道を入り山門をくぐる。文安5年 |
| (1448)日泰上人によって創立された日蓮宗寺院である。参道を戻り通りを渡るともう三嶋大社だ。 |
| 大社鳥居東よりに標識と標柱が建って伝馬町の跡を示していた。 |
 |
 |
 |
 |
| 三嶋大社 | 下田街道 | 農兵調練場跡 | 代官所跡(三島市役所) |
| 三嶋大社の正面から南に伸びる道が下田街道である。新しい道は国道136号となって大社の西脇 |
| から国道1号と立体交差して天城方面に南下している。この旧道は二日町から大場で韮山往還と |
| 分かれ原木・大仁を通り天城方面に続く。また、大社の西側を北方向に向うのは佐野街道として、 |
| 幸原から佐野・裾野方面に伸び、足柄街道に合流している。南西側に建つ三島市役所は宝暦9年 |
| (1759)に韮山代官所に統合されるまでの代官所跡で、またこの地には嘉永5年(1852)江川 |
| 坦庵が洋式の軍事調練場(農兵調練場)を設けた跡の石碑も建っている。 |
 |
 |
 |
 |
| 福聚院 | 唐人町通り | 問屋場跡(郵便局) | 問屋場跡の説明板 |
| 唐人町通りの近くにあるが、あまり目立たなくてつい通り過ぎる所に福聚院はあった。紀州徳川家が |
| 非常の際の場所に指定されたということで葵の紋がついた幕があるらしい。唐人町という名は朝鮮 |
| 使節の往来の際に随行者がこのあたりに宿泊したことからこう呼ばれている。唐人町通りを旧街道に |
| 出ると、向かい側郵便局がある所に問屋場跡の説明板が建っていた。慶長6年宿場が設置された |
| 当時から有数の大宿であった三島宿は大勢の人足、役人がいて問屋場の周囲には人足、飛脚 、 |
| 賄人、馬指などの部屋があった。 |
 |
 |
 |
 |
| 御殿川と御殿橋 | 御殿神社 | 大和屋脇本陣跡(本町南東角) | 銭屋脇本陣跡(本町北東角) |
| 問屋場前から本町交差点との間に小さな川が流れていて、小浜池あたりの湧水が御殿川と呼ばれる。 |
| 旧街道に架かる御殿橋から西一帯が御殿地域で、元和9年(1623)に将軍家光上洛の折御殿が |
| 新築された。今では広大な敷地の名残として周囲に石垣の跡があり跡地には御殿神社が祀られて |
| いる。御殿橋からすぐ西の三島市中心部、本町交差点は当時も宿場の中心部であった。交差点の |
| 北東角、竹沢電機あたりが銭屋脇本陣、その向かい南東角の丸中家具店あたりが大和屋脇本陣 |
| の跡だと推定される。 |
 |
 |
 |
 |
| 世古本陣跡(本町北西角) | 樋口本陣跡(本町南西角) | 綿屋脇本陣跡(世古本陣西) | 四ノ宮川と四ノ宮橋 |
| 交差点を渡り北西角のクリタメガネ店からみずほ銀行にかけてこのあたりに世古本陣(一の本陣)が |
| あったらしく小さな石柱が建てられている。また、二の本陣として向かい側山田園あたりに樋口本陣、 |
| 歩道上に「樋口本陣跡」の石柱がある。綿屋脇本陣の跡には大きなタワーズショップ、世古本陣 |
| との間を流れる小さな四ノ宮川は小浜池から源兵衛川から分流した川で、街道の南側は御殿地 |
| の西にあたる。 |
 |
 |
 |
 |
| 常林寺 | 源兵衛川と源兵衛橋 | 三石神社 | 時の鐘 |
| 宿場の中心部を過ぎ広小路に向かう。源兵衛川の左岸には参道は細いが境内に入ると街中に |
| このような広い寺地があったというくらいの寺院。曹洞宗常林寺である。川を挟んで右岸に三石 |
| 神社。ここには観光地となっている時の鐘がある。時の鐘は寛永年間に初めて鋳造されさらに |
| 宝暦11年(1761)になって浄財を集めて大鐘を鋳造して神社境内に建立された。 |
 |
 |
 |
 |
| 広小路火除土手跡 | 林光寺 | 西見付跡(秋葉神社) | 西見付火除土手跡 |
| 広小路は江戸時代初期の頃は三島宿の西の入口であった。その当時火災の延焼を防ぐために土手を |
| 築いていたようだが今は全くその形跡はない。おそらく伊豆箱根鉄道の線路になっているあたりでは |
| ないだろうか。広小路駅前で道は二股に分かれる。右は新道で旧街道は左側を辿る。やがて加屋町 |
| (茅町)に入る。ここが三島宿の西端であった。ここには林光寺という浄土宗の寺院。武田氏縁の寺院 |
| で天正5年(1577)創立という。林光寺を過ぎて南西側にある秋葉神社に到着する。西見付の跡だ。 |
| 神社裏にはそれらしい土手があって民家が建ち並んでいるが、当時の防火土手のままだろうか。 |
 |
 |
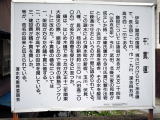 |
 |
| 境川橋 | 千貫樋 | 千貫樋の説明板 | 甲州街道入口 |
| 秋葉神社の西側を流れる境川。三島宿が終わり沼津宿に向かうが、街道の北側には小浜池から |
| 伏見村まで引かれた用水樋「千貫樋」が今ではコンクリート製になったが残されていた。また、境川橋 |
| のすぐ西側の交差点は北に入る甲州街道の入口である。 |
 |
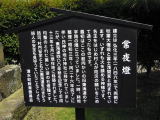 |
 |
 |
| 常夜燈 | 常夜燈の説明板 | 新宿の標識 | 街道に残る古民家 |
| 三島宿をじっくり回ったためこの区間は2回に分けて歩いた。2回目は三島宿西見付からスタート。 |
| 甲州街道入口交差点からすぐ右手の公園になった所に常夜燈が建てられている。筋向いの交差点の |
| 隅にあったものを近年移転したようだが、元々弘化3年(1846)の制作である。この地は沼津宿境 |
| まで1里の新宿(清水町新宿)。さらに西に歩を進めるとこのあたりにはまだ当時を思わせるような古 |
| 民家が残っている。 |
 |
 |
 |
 |
| 玉井寺 | 白隠の遺墨 | 宝池寺 | 宝池寺本堂 |
| 国道1号に出るすぐ手前変則交差点の両側に向かい合って2つの寺院が建っている。まず右手、北側 |
| の玉井寺。ここには白隠の遺墨として三界萬霊等と山号寺号が残されている。この玉井寺山門脇に |
| 伏見一里塚(北塚)が保存されていた。南塚は崩落があり一部改修されたが、この北塚は旧態をとど |
| めているようだ。 |
 |
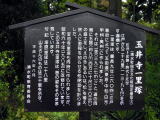 |
 |
 |
| 伏見一里塚(北塚) | 玉井寺一里塚(北塚)説明板 | 伏見一里塚(南塚) | 宝池寺一里塚(南塚)説明板 |
| 玉井寺の向かい側に宝池寺がある。山門前広くなった駐車場の真ん中にきれいに保護された一里塚 |
| が堂々とその姿を現していた。一部改修されたこの南塚は宝池寺山門・本堂をバックに絵を描きたく |
| なるような所だ。江戸から29番目の一里塚、28番目の錦田一里塚とともに両側が残る貴重な塚で |
| ある。 |
 |
 |
 |
 |
| 旧街道と国道の交差点 | 八幡神社 | 八幡神社境内 | 対面石 |
| 一里塚を過ぎるとすぐに国道1号と交差する。国道は旧街道三島宿のバイパスとなって三島の塚原 |
| からまっすぐ西に向かいここ清水町八幡で旧街道と出合う。旧街道は国道を横切りS字に西へ向か |
| う。やがて右手に八幡神社の看板と鳥居。八幡神社の奥、拝殿の脇に竹垣で囲まれた2つの大きな |
| 石が向かい合っていた。治承4年(1180)富士川の戦いに出陣した源頼朝と駆けつけた義経兄弟 |
| が対面した石と伝えられている。 |
 |
 |
 |
 |
| 清水町長沢に残る松並木 | 黄瀬川(木瀬川)と黄瀬川橋 | 黄瀬川橋下の石仏群 | 木瀬川宿 |
| 神社境内を出て沼津宿に向かう。街道左側に一部残る長沢松並木。ゆるく左カーブして黄瀬川を |
| 渡る。橋の下に石仏が並んでいる。下りてみると蛇塚・庚申塔・観音菩薩・地蔵菩薩等々、中には |
| 明和5年(1768)と刻まれたものもあった。橋を渡ると古代・中世の木瀬川宿のあったあたり。江戸 |
| 時代には立場があったようだ。ここから現代では沼津市に入る。 |
 |
 |
 |
 |
| 潮音禅寺 | 傍示杭 | 下石田交差点で合流 | 駿府へ15里の表示柱 |
| 右手に潮音禅寺が見えてくる。臨済宗の禅寺だがここには亀鶴姫の伝説があり、幼い時に両親を |
| 亡くした駿河の三美人といわれた姫が頼朝の応召を断り黄瀬川に身を投げたという言い伝えが |
| 残って墓石や供養塔が建てられている。やがて右手に傍示杭、ここより西が沼津領となる。この先で |
| 旧国道と合流する。しばらく旧街道は広い旧国道1号(県道380号)を辿る。途中駿府へ15里という |
| 石柱を見かけた。 |
 |
 |
 |
 |
| 狩野川沿いの旧道 | 平作地蔵 | 沼津一里塚 | 玉砥石 |
| 合流地点(沼津市大岡)から沼津の中心部に入ってくる。ここで旧街道は狩野川沿いの細道に入る。 |
| 日本三大仇討ちの一つ平作を祀った地蔵尊を見て少し行くと右手に小公園。そんなに高くない沼津 |
| 一里塚が見えていた。沼津宿絵図では山王前の街道と参道の交差するあたりに書かれているので |
| よく見ると公園脇の細い道が参道で向こうに鳥居が見えている。沼津一里塚は30番目でどうやら |
| 北塚のようだがもう一方は現存していない。またここには古墳時代に玉を砥いだという玉砥石が置か |
| れているが貴重な考古資料のようである。 |
 |
 |
 |
 |
| 日枝神社参道入口 | 日枝神社参道 | 日枝神社 | 境内の芭蕉句碑 |
| 一里塚脇の細い参道を入り県道380号を渡った先が日枝神社(山王)だ。ここから西に沼津宿に |
| 入ってくる。 |