 |
 |
 |
湯河原町・素鵞神社例大祭
 |
 |
 |
| 撮影日 2015, 8, 1 |
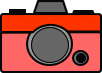 |
| アルバム |
| 1 神社 |
| 神社名 素鵞神社(すがじんじゃ) |
| 所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1047番地 |
| 創建 元和六年(1620) |
| 社格 旧村社 |
| 祭神 素佐之男神(スサノオノカミ) |
| 伊弉諾神(イザナギノカミ) |
| 伊弉冊神(イザナミノカミ) |
| 神紋 五瓜に唐花紋 左三つ巴紋 |
| 由緒 元和6年創建の他は不詳。明治6年に村社に列せられる。他熊野神社 |
| 2社を合併。大正12年9月1日関東大震災により拝殿が全壊する。 |
| 大正15年に拝殿幣殿を改築、昭和15年8月現在地に移転社地を |
| 拡張する。 |
| 2 祭典日程 |
| 8月1日 (訪問日 2015, 8, 1) |
| 【8月1日】 9:00 例祭式 浦安の舞奉納 10:00 鹿島踊り |
| 10:30 神輿宮出し 町内巡行 |
| 3 山車・屋台 詳細 → 詳細ページへ(置き屋台) |
| 屋台蔵右側 小田原型山車 |
| 屋台蔵左側 小田原型山車 |
| 4 所感 神奈川県湯河原町の素鵞神社は湯河原の市街地東部の湯河原海水浴場の |
| 真ん前にある。例祭日が8月1日ということで、海水浴客がごった返す中で祭典が |
| 行われる。 |
| 朝8時半に到着したがもう暑さ厳しく車を役場駐車場に置かせてもらって神社まで |
| 15分程歩く。海岸線を通る国道135号から50m程入った石段を上ると左右に屋台蔵 |
| があって、いかにも年代ものの屋台(形は小田原型山車)が収納されていた。 |
| 左の屋台蔵の奥に手水舎、右の屋台蔵の奥は広場になっていてここで鹿島踊りを |
| 演じるようだ。 |
| 9:00になり例祭式が始まる。拝殿の前までさらに石段を上り、向拝脇から中の様子を |
| 撮影することにした。式典の後、巫女4人による「浦安の舞」を奉納。舞が終わって |
| 白丁姿の男たちが拝殿前に上がってくる。裃姿の役員4名の他、20名くらいいようか、 |
| 全員向拝で神主の修祓を受ける。 |
| 10:00屋台蔵前の広場で「鹿島踊り」が始まる。鹿島踊りは茨城県鹿島神宮から |
| 始まり、関東・湘南・伊豆東海岸など海岸線に広まった男たちの踊りである。その起源 |
| については疫病退散・五穀豊穣を願ってのものであるが、この地や東伊豆では |
| 石材運搬の無事を願ってという説もあるようだ。県の無形民俗文化財及び国の選択 |
| 無形民俗文化財に指定されている。約30分で鹿島踊りが終わり、宮神輿の宮出しが |
| 始まる。屋台蔵の屋台は今では置き屋台(飾り屋台)になっていて曳かれることはない。 |
| 鹿島踊りの見学はもちろんだが、今回の目的は拝殿彫刻(寛政4年)と屋台彫刻 |
| (天保13年)における通称「波の伊八」と言われた安房の名工、初代武志伊八郎の |
| 作品を見るのが第一の目的であった。 |
| 宮出しを済ますと境内は先程の賑わいがウソのように静まり返っている。これから |
| 2台の屋台彫刻と拝殿彫刻の撮影にじっくりとりかかることができた。 |
| 寛政4年(1792)の蟇股の龍、223年前41才時の作品だ。そして、天保13年(1842) |
| の銘が共作者の後藤三治郎恒俊の欄間に残されているが、屋台小脇の「上り龍」 |
| 「下り龍」、せいご台欄間の「浪に亀」などは伊八の没年が文政7年(1824)ということ |
| から後藤恒義の欄間より以前に彫ったことになろうか。いずれにしても「波の伊八」と |
| いわれるくらいの龍・浪の出来栄えであった。無論、共作の後藤恒俊とて日本橋、 |
| 東都後藤本流の名工でその作品の素晴らしさは言うまでもない。 |