 |
 |
 |
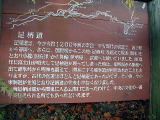 |
| 足柄峠万葉公園駐車場 | 聖天堂向い側の古道入口 | 足柄古道入口 | 足柄道説明板 |
足柄古道(足柄峠〜関本)
| 日時・行程 |
| 2005年11月26日 |
| 足柄峠(南足柄市県境) 〜 聖天堂前(古道入口) 〜 腰掛石 〜 見晴台 〜 |
| 相の川橋 〜地蔵堂 〜 長者橋 〜 矢倉沢定山 〜 県道合流点 〜 |
| 家康陣場の跡 〜矢倉沢関所跡 〜 東山 〜 足柄神社 〜 苅野駐在所 〜 |
| 白地蔵 〜 弘西寺入口 〜 関本 〜 大雄山駅(南足柄市) |
| 地図 |
 |
 |
 |
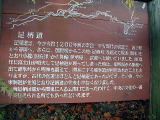 |
| 足柄峠万葉公園駐車場 | 聖天堂向い側の古道入口 | 足柄古道入口 | 足柄道説明板 |
| 前回は足柄峠まできて金時山から仙石原に下り御殿場に戻った。第4回目は林道足柄峠線を車で来て |
| 足柄万葉公園駐車場に置く。そして峠から関本へ伊豆箱根鉄道大雄山駅までを歩く。駐車場から少し |
| 峠に戻り聖天堂の向い側に古道入口の標識を見つけた。ここが今回の出発点となる。 |
 |
 |
 |
 |
| 古道入口下 | 源頼光の腰掛石 | 腰掛石の説明板 | 古道には所々石畳が残る |
| 古道入口から下るとすぐに小山のような大きな岩がある。側には説明板があるが文字はほとんどが |
| 消えた状態で見えない。どうやら源頼光の腰掛石の説明のようである。足柄で育った金太郎伝説から |
| 言えば頼光四天王となった坂田金時と会った頼光が腰をかけたということのようだ。このあたりにも |
| 所々石畳が敷いてあるが官道として使われていた時のものではないだろう。 |
 |
 |
 |
 |
| 見晴台 | 見晴台に建つ古道案内図 | 見晴台から明神ヶ岳を見る | 見晴台から見た金時山方面 |
| 樹林帯から出たところが見晴台。県道でバス停があり、東屋が建てられていて休憩所になっていて、 |
| コース案内図や古道説明板もある。ただやはり説明板の文字が消えかかっていて不明だ。見晴台 |
| というくらいで眺望がすこぶるよい。振り返って金時山から箱根外輪山の明神ヶ岳までの稜線がよく |
| 見えていた。 |
 |
 |
 |
 |
| 県道78号を歩く | 古道は県道を絡むように続く | 相の川橋を過ぎ地蔵堂に向う | 地蔵堂手前からの矢倉岳 |
| 見晴台からはしばらく県道を歩く。神奈川県側は交通量も多く車に要注意だ。紅葉したカエデ・クヌギ |
| ミズナラや桧・杉の針葉樹。快適に歩を進めると道路脇に標識が建つ。県道から混交林の中に古道は |
| 入っていく。やがて傾斜が緩くなり道も広くなって相の川橋を渡って地蔵堂に向かう。紅葉した尾根の |
| 上に矢倉岳が顔を出していた。 |
 |
 |
 |
 |
| 地蔵堂 | 地蔵堂から夕日の滝方面に向う | 長者橋手前の坂道 | 長者橋 |
| 下りのせいか早くも地蔵堂に到着する。足柄峠古道入口から40分程度。地蔵堂からは県道78号が |
| まっすぐに下っているが、古道は若干上り加減に夕日の滝方面に向かう。長者橋手前の緩い上りが |
| 今日の唯一の上りか。まもなく15分程度で長者橋に着く。 |
 |
 |
 |
 |
| 長者橋を渡り林道に入る | 長者橋から見た矢倉岳 | 林道の分岐を左に折れる | 古道下りから足柄峠を振り返る |
| 長者橋で夕日の滝コースと別れ橋を渡る。ここから古道は林道に入っていく。5分程で分岐があり左に |
| 折れる。下り途中で足柄峠を振り返るともう大分下ってきたことがわかる。足柄峠の標高が約750m |
| 位だと思うが、地蔵堂下で400m位だからおよそ350m下って来たことになるようだ。 |
 |
 |
 |
 |
| 頼朝のひじ松説明板 | 矢倉沢定山の説明板 | 定山の遺構は藪で不明 | 1段高く歩道が整備されている |
| 長者橋から15分程度下ると右手に説明板。源頼朝がここで月を鑑賞する時に松の枝が邪魔で折り、 |
| その枝が曲げた肘のようだからというひじ松の説明だが、なぜ夜に頼朝がここを通ったのかはわから |
| ない。ここから8分で定山。古道脇に矢倉沢定山の半分割れた説明板があるだけで、定山の城跡の |
| 遺構など全くわからなかった。道から一段高くなった藪の中にはとても入れずあきらめる。まわりは |
| 黄葉した雑木林と松・桧・杉それに所々にシキミ。このあたりは歩道が整備されていた。 |
 |
 |
 |
 |
| 下り勾配は15% | 古道が県道に合流 | 合流地点のバス停 | 合流地点の石仏 |
| ゆっくりと下ってきた道が県道に合流する手前でやや急になる。定山から15分で県道78号の足柄 |
| 古道入口というバス停に出た。バス停上段には石仏が祀られている。ここからはもうほとんど山道は |
| 終わり、県道を巻きつくように農道を下っていく。 |
 |
 |
 |
 |
| 家康陣馬の跡説明板 | 古道は県道と離れ畑地に入る | 茶畑の上の矢倉岳 | 古道沿いのあざやかな紅葉 |
| 5分程休憩の後、県道を下っていくと家康陣馬の跡と書かれた説明板が建っている。まさに天正18年 |
| (1590)の小田原攻めにおける徳川軍の行軍ルートを辿ろうとしているわけだが、家康本隊は箱根 |
| 越えしていて足柄は先鋒隊の井伊直政隊ではなかっただろうか。しばらく歩くと左側に小さな足柄古道 |
| の標識。ここから県道と離れ畑地に入っていく。やや上って出たところは茶畑の上に大きく矢倉岳が |
| 正面だ。あたりも紅葉がまぶしいほどに鮮やかである。 |
 |
 |
 |
 |
| ミカン畑から県道に下りる | 県道を横切った所の石塔 | 県道と並行した細道を下る | 道端に祀られた双体仏 |
| 茶畑からミカン畑に変わり農道から再び県道に下りる。県道を横切った先に大きな石塔。左手に県道 |
| と並行した細い道を下る。石塔といい道端に祀られた双体仏といい、いかにも古道の往来で古の人々 |
| が手を合わせている姿が思い浮かぶようである。 |
 |
 |
 |
 |
| 矢倉沢関所跡 | 矢倉沢関所跡の説明板 | 東山バス停の石仏群 | 東山バス停に建つ芭蕉句碑 |
| 矢倉沢からは松田を経由して江戸までの矢倉沢往還がありました。そのためここには関所を設けた |
| ということで、何も残っていないが関所跡の説明板が建っていた。県道東山バス停に出ると石仏群、 |
| 松尾芭蕉の句碑が建っている。また往還の関所があったことから関場の旅籠宿が栄えたらしい。 |
 |
 |
 |
 |
| 東山で県道から農道を登る | ミカン畑から下り舗装道路を右折 | 矢倉岳と足柄峠を振り返る | 足柄神社手前のミカン畑 |
| バス停の所で県道を横切り農道を登って行く。両側はミカン畑。ちょっと下って広域農道を右折する。 |
| 小さな道標に誘われるように古道を辿る。農道もあたりが広くなった所で振り返ると矢倉岳と足柄峠 |
| が見えている。さらに足柄神社まで色づいたミカン畑の中を進んで行く。 |
 |
 |
 |
 |
| 足柄神社 | 足柄神社由緒碑 | 足柄神社観音堂 | 観音堂の説明板 |
| 関所跡からのんびり歩いて50分程で足柄神社に着く。境内には石版の由緒碑が建っている。祭神 |
| はどうやら日本武尊命のようだ。拝殿の彫刻に見とれながら境内の脇を見ると観音堂が建てられて |
| いた。観音堂にはしっかりと説明板が付けられていて、足柄明神の本地仏である聖観世音菩薩を |
| 祀ってあるという。ここの向拝にもいい彫刻が付けられているがいずれも銘がなかった。 |
 |
 |
 |
 |
| 足柄神社から県道に出る | 県道78号苅野駐在所前 | 駐在所前の白地蔵 | 白地蔵の説明板 |
| 足柄神社の参道を下ると県道78号に出る。苅野駐在所前のバス停であった。もうここからは県道を |
| 歩き山道はない。駐在所の前に小祠があって中に1体の地蔵が祀られていた。説明板によると白地蔵 |
| (または化粧地蔵)というそうで、安産と授乳に霊験があるらしくそのお礼参りに小麦粉を地蔵の身体に |
| 塗りつけるという慣習があることからこう呼ばれている。 |
 |
 |
 |
 |
| 弘西寺 | 弘西寺入口の石塔群 | 県道78号関本の交差点 | 伊豆箱根鉄道大雄山駅 |
| もう後はひたすら県道を歩いて関本に向かう。途中弘西寺入口に石仏・石塔群を見る。関本の竜福寺 |
| 交差点で御殿場市役所から長いこと県道78号の足柄街道を歩いてきたが、78号と分かれて右折。 |
| 県道74号を今度は小田原に向かって行くことになる。本来足柄古道は関本で矢倉沢往還と分岐して |
| 国府津に向かう道であるが、ここでは当初の予定通り関本から小田原攻めの徳川軍が行軍したコース |
| を行くため県道74号を辿り小田原の家康陣場跡までのコースを取る。交差点を右折してすぐに伊豆 |
| 箱根鉄道の大雄山駅が見えて今回はここまでとする。 |