 |
 |
 |
 |
| JR御殿場線足柄駅 | 駅前の踏切を渡る | 踏切先の分岐 | 直進する林道戦返線は通行止 |
足柄古道(小山〜足柄峠)
| 日時・行程 |
| 2005年11月20日 |
| 足柄駅(駿東郡小山町) 〜 馬喰坂 〜 竹之下一里塚 〜 林道金時線分岐 〜 |
| 唯念上人碑 〜伊勢宇橋 〜 水飲沢 〜 足柄古道標識 〜 県道出合 〜 |
| 下六地蔵 〜 上六地蔵 〜 足柄峠(駿東郡小山町県境) |
| 地図 |
| 国土地理院地形図(御殿場・関本) ゼンリン地図(小山町) |
 |
 |
 |
 |
| JR御殿場線足柄駅 | 駅前の踏切を渡る | 踏切先の分岐 | 直進する林道戦返線は通行止 |
| 第3回目はJR御殿場線足柄駅をスタートに足柄峠までを設定した。駅前の踏切を渡り東方向へ。ただ |
| 予定していた林道戦返線は落石のため通行止めになっていた。標識にも戦返線が足柄山古道と書か |
| れているので残念だ。 |
 |
 |
 |
 |
| 分岐に建つ標識 | 右折した県道にある馬頭観音 | 県道から馬喰坂に入る | 馬喰坂の標識 |
| 分岐で県道78号方面に迂回する。峠までの所要時間はいずれのコースをとっても90分とある。戦返 |
| 線コースと78号線コースと途中で合流するようだ。分岐を右折して大正15年と比較的新しい馬頭観 |
| 音を見ながら馬喰坂。このあたりは馬喰達が住んでいたということらしい。馬喰坂の標識を県道と分か |
| れて左折し坂を上っていく。 |
 |
 |
 |
 |
| 馬喰坂上の嶽之下神社 | 鳥居脇の石仏 | 神社上から見た竹之下 | 神社上にある天保年間の石仏 |
| 5分程坂を上ると右手に鳥居が見える。嶽之下神社が祀られていた。しかし境内には焼失した社殿の |
| 跡のみで平地となっていて再建されていない。鳥居脇の庚申塔や街道筋の石仏群がやはりこの道も |
| 古くから峠まで通っていたことを思わせる。 |
 |
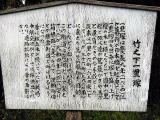 |
 |
 |
| 竹之下一里塚で県道に合流 | 竹之下一里塚説明板 | 一里塚から見た富士山 | 県道78号を登る |
| 坂を通り抜けると県道78号に合流。左手を見ると1枚の説明板が建っていた。見ると一里塚跡のよう |
| だ。有闘坂上の一里塚からここまで1里ということか。やはりこの道が官道として箱根路を使う以前の |
| 中世までの東海道か。一里塚から振り返って見た富士山の姿が美しい。ここからしばらくは県道を |
| 上ることになる。 |
 |
 |
 |
 |
| 林道金時線との分岐 | 分岐に建つ標識 | 林道竹之下金時線 | 金時線も通行止になっている |
| しばらく紅葉を眺めながらほとんど車の通らない舗装道路を上っていくと右手に林道の分岐。竹之下 |
| 金時線だが、すぐ先に通行止の看板が立てられている。このあたりの林道は風雨によりだいぶ荒れて |
| いるようだ。このすぐ上段に日蓮聖人の題目碑があるようだが寄り道せずに県道を上る。どうやら |
| 12世紀ごろ日蓮も身延山に入山する時この道を通り竹之下に宿泊していたようである。 |
 |
 |
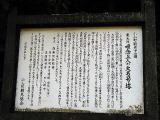 |
 |
| 金時線分岐上の紅葉 | 唯念上人大名号碑 | 大名号碑の説明板 | 大名号碑前の栗の木沢 |
| 林道金時線分岐のすぐ上の街道沿いに唯念上人の念仏碑を見る。天保元年(1830)飢饉と疫病から |
| 村人達を救うため「南無阿弥陀仏」の念仏を唱え、村人達が天保10年に大名号碑を建てたという。現 |
| 在小山町の指定文化財になっている。大名号碑の前は栗の木沢の清流が流れやがて伊勢宇橋を渡 |
| る。 |
 |
 |
 |
 |
| 伊勢宇橋 | 伊勢宇橋の説明板 | 橋の脇に戦返線への分岐 | 分岐に建つ標識 |
| 地蔵堂川を渡る伊勢宇橋は説明板によると、浅草の商人伊勢屋宇兵衛が交通不便なところに財を |
| 投じ橋を架けていったという。伊勢宇橋がその85番目の橋だと書かれていた。橋を渡った左手には |
| 足柄駅から通行止になっていた戦返線と出合う。標識によると足柄峠まで40分とあり今日の行動 |
| 予定のほぼ中間点である。 |
 |
 |
 |
 |
| 戦ヶ入の標識 | 戦返線分岐上の水飲沢 | 水飲沢上に古道入口 | 足柄古道の標識 |
| 林道戦返線分岐点の上に竹之下合戦の戦ヶ入という標識。戦地跡の史跡から林道名も戦返線と |
| なったものか。すぐ脇に1本の沢があり水飲場となっている。峠越えする旅人の峠まで最後の水飲み |
| 場になっていた。10分程上って左手に石畳の道が見えてくる。その分岐に足柄古道の表示杭が |
| 建つ。この石畳は当時のものではなく完全に新しく敷かれたものである。 |
 |
 |
 |
 |
| 古道に入った所の馬頭観音 | 馬頭観音の説明板 | 足柄古道 | 竹之下を見下ろす |
| 県道と分かれた古道に入る。石畳はすぐに終わり上段に馬頭観音が祀られている。説明板によると |
| 古道は1000年以上も経つそうで古代から往来も頻繁で相模から甲斐へと塩を送る道にもなっていた |
| ようだ。また陶器に使う赤土が採れたことから赤坂とも言われたという。ここからはやっといかにも古道 |
| という風景になってくる。 |
 |
 |
 |
 |
| 県道を横切りまた古道に入る | 県道足柄峠線に出る | 県道に出た所の標識 | 県道上段の芭蕉句碑 |
| 古道は途中県道を横切りさらに上っていく。古来からの峠までの道に対して新しい舗装された車道が |
| 古道を分断しながら峠まで上って行っていると言ったほうがいいのかもしれない。足柄古道の表示杭 |
| から20分で県道足柄峠線365号に出る。反対側に芭蕉の句碑。県道はすぐ手前で下から上ってきた |
| 県道78号と合流して78号として峠を越え神奈川県に下っているのだ。 |
 |
 |
 |
 |
| 下六地蔵 | 上六地蔵 | 足柄城下の念仏碑 | 足柄峠 |
| 句碑からは県道を辿り回り込んだ上に下六地蔵といわれているが8体の地蔵が祀られている。さらに |
| そこから50〜60m位も上るともう1ヶ所の地蔵。上六地蔵といわれている。ここには6体の舟形向背 |
| に浮き彫りされた石地蔵。下六地蔵の祀られた年代は享保年間らしい。ここまでくると峠はもうすぐ上 |
| である。足柄城址の下段の念仏碑を拝みながら回りこんで足柄峠に到着する。足柄駅を出てから約 |
| 1時間35分ほどであった。 |