 |
 |
 |
伊勢原・比々多神社例大祭
 |
 |
 |
| 撮影日 2015, 4, 22 |
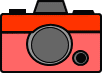 |
| アルバム |
| 1 神社 |
| 神社名 比々多神社 |
| 所在地 神奈川県伊勢原市三ノ宮1472番地 |
| 創建 伝 神武天皇6年(紀元前655年) |
| 社格 式内社 相模国三之宮 郷社 |
| 祭神 豊国主尊(トヨクニヌシノミコト) |
| 天明玉命(アメノアカルタマノミコト) |
| 稚日女尊(ワカヒルメノミコト) |
| 日本武尊(ヤマトタケルノミコト) |
| 神紋 十六菊紋 五三の桐紋 |
| 由緒 神武天皇六年国土創建民族興隆を祈念し日本国霊として当社を創建 |
| したと伝えられる。崇神天皇の御代神地神戸を奉られ大化元年(645) |
| 社殿修復の際、木彫の狛犬一対(市重要文化財)を奉納又此年に |
| 酒解神を合祀、うずら瓶(県重要文化財)を納められた。天平十五年 |
| (743)大宮司に竹内宿禰の後孫紀朝臣益麿を迎えて初代宮司に |
| 任命勅して荘園を賜う。南北朝室町時代に戦さに巻込まれ神領の |
| 大半を失い衰微したが徳川時代当社が相模国の名社であることを |
| 知った家康公より社領を新に寄進され以下十四代将軍まで続いた。 |
| 2 祭典日程 |
| 4月22日 (訪問日 2015, 4, 22) |
| 【4月22日】 10:00 例祭式 12:50 三之宮青年宮詰 12:55 桑原青年宮詰 |
| 13:00 神戸青年宮詰 13:10 行列出発 14:00 神戸渡し |
| 14:25 行在所御着の式 15:00 御立の式 16:00 三之宮渡し |
| 17:05 鎮座祭 |
| 3 山車・屋台 詳細 → 詳細ページへ |
| 三之宮 四輪一本柱万度型人形山車(人形 加藤清正) |
| 栗原 四輪一本柱万度型人形山車(人形 熊谷次郎直実) |
| 神戸 四輪一本柱万度型人形山車(人形 歌舞伎伽羅先代萩の男之助) |
| 4 所感 伊勢原比々多神社には昨年(2014)の例大祭に行く予定をしていたが、急用ができ |
| て断念、1年待って今年の4月に行くことができた。 |
| 車で国道246号を厚木方面に向って走り、秦野を過ぎ伊勢原に入るとすぐ東名高速の |
| ガードをくぐって左側に入る。比々多の交差点は祭典中、すぐ北にお旅所を設ける |
| 関係もあって入ることはできない。その1つ東の工業団地入口交差点を北に折れて |
| 東名高速のガードをくぐると比々多神社入口の表示が見えてくる。 |
| 氏子町内は神社周辺の三之宮、栗原と南側の神戸との3町内である。従って宮神輿 |
| の渡御も三之宮・栗原から神戸に入った所で「神戸渡し」という式を行って、神戸区内 |
| にある行在所(お旅所)に向かう。 |
| 10時からの例祭式に間に合うように神社に着いたが、拝殿内はやや高くなっている |
| ために中の様子はわからなかった。神輿の宮出しが昼からなので、その間に渡御の |
| コースの確認やら周辺の状況の確認を行なう。神戸へのコースの途中の道路端で |
| 3台の山車の組立作業に立ち会えたのは幸運であった。湘南独特の径の小さい |
| 4輪の上に台輪、柱を立て格子状に組んだせいご台の上に囃子台。その真中に幕・ |
| 万度を付けた1本柱、柱の最上部に人形をつけて囃子台のセンターに立てる。 |
| 山車後部から立ち上げるのだが、柱の上部にロープを縛り山車前方から数人の力で |
| 引き上げる。こうして立ち上げた万度・人形に放射状に水垂などの山車飾りをつけて |
| いくようだ。このように比々多神社の山車は一本柱万度型の山車でも初期の物を |
| 思わせるような簡易な造りであった。 |
| やがて例祭式から神輿渡御に移る前に担ぎ手の青年たちは潔斎をするのだが、後を |
| ついて行ってみると少し離れた能満寺の下で藁を積み上げていた。それを囲んで |
| お神酒を交わし積み上げた藁に点火。皆それぞれにその火を飛び越えて潔斎する。 |
| そうやって意気揚々と三之宮の青年から順次宮詰して神輿の宮出しを行っていた。 |
| 供奉行列は役員を先頭に金棒、高張、錦旗、猿田彦、五色旗、大榊、長持ち、御幣、 |
| 神社旗、祭主(神主)、そして神輿が続く。 |
| 祭典自体は小ぢんまりして山車も旧来の一本柱万度型の簡易的な造りだけれど、 |
| さすがに相模国三之宮という格式のある神社の例祭らしく神事・供奉行列など、 |
| きっちりとした祭礼は見ごたえのあるものだった。 |
| 行在所まで神輿について行ったが、発輿祭から帰り神社に戻る時間は舞殿での神楽 |
| と重なったので相模里神楽を見学に神社に戻る。演目は「天岩戸」の神楽であった。 |